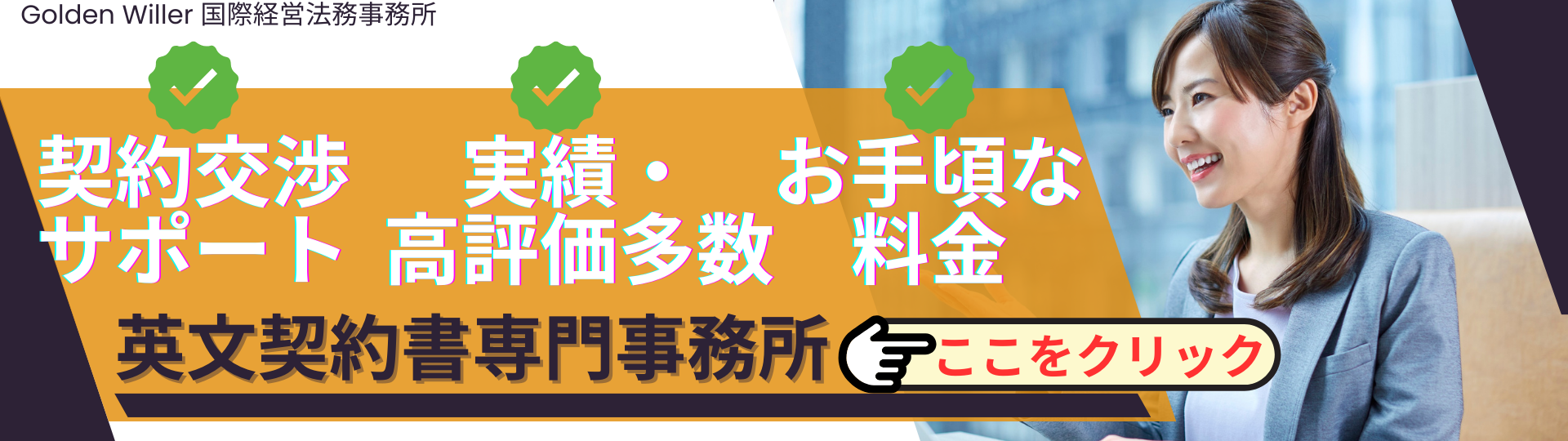英文契約書の仲裁(arbitration)をわかりやすく解説します
仲裁(arbitration)とは?
仲裁とは、裁判によらず、当事者が定めた仲裁人に紛争処理を委ねることを言います。
国際的な取引で使用される英文契約書では、裁判管轄や仲裁条項は必ずと言ってよいほど、契約書に記載されます。
仲裁は裁判と違い、弁護士費用や裁判費用等のコストが少なく、また、紛争解決までの時間が裁判に比べて短いという特徴があります。
また、仲裁の判断を最終のものとすることが出来、その判断に基づいて、相手方の財産に対して強制執行が可能となります。
但し、外国に所在の当事者への財産に強制執行する場合にはその国のニューヨーク条約への加盟を確認してください。
日本国内にも仲裁の専門機関があります。
オンライン仲裁(Virtual Hearing)
昨今はコロナ禍のため海外への渡航が困難な場合がありますので、国際的な取引の場合、仲裁開催地を外国にすることをためらう場合もあります。
相手方当事者も同じ悩みがあるかと思います。
そのようなときに利用したいのが、オンライン審問と呼ばれるオンラインによる仲裁です。
オンラインですので、相手方国に渡航する必要がなく、費用や時間、感染リスクをより削減できるものですので、国際的な仲裁において今後はより活用されるべきものといえます。
日本では東京と大阪の仲裁機関でオンラインによる仲裁が可能です。
仲裁の効力
仲裁人が、合法的に選ばれ(仲裁法一七条)、手続きが合理的に進められれば(同法五章各条)仲裁判断は、当事者間においては確定判決と同一の効力をもちます(同法四五条)。
したがって、非常に強力な履行確保の方法になります。
さらに、強制的に相手方に履行させ得るような趣旨の仲裁判断(たとえば、OOは金OO円を支払え、とか、OOは後記土地を明け渡せ、など)が盛りこまれていれば、裁判所に申し立てて、執行決定(強制執行を許す、という裁判所の判断)をもらうことができます。
そして執行官に委任して動産の差押えや、明渡しなどの執行もできます(同法四六条)。
仲裁条項の記載についての注意点
仲裁であれば、専門家による迅速で非公開の裁定を受けることが出来ます。
但し、裁判所の裁判と違い、一審制ですので仲裁人による判断に不服がある場合においても、その判断を同じ仲裁機関で争うことは出来なくなります。
そして、仲裁機関の裁定に不服がある場合には通常の裁判所への訴訟提起を起こすことが可能となるのですが、これを許してしまうと、紛争が長期化してしまいます。
ですので、「仲裁人の判断が当該紛争につき最終的な判断である」と契約書に規定するほうがよいかと思います。
また、仲裁条項を定める場合には、仲裁機関を決定することと共に、仲裁規則についても決定してください。
取引相手が米国の場合の仲裁のメリット
また、取引相手が米国の場合において仲裁を選択するメリットとしましては、陪審員による事実認定が行われないということが挙げられます。
一概には言えませんが、陪審員は一般人でありときには感情的な判断を下す恐れもありますので、自国民を有利に判断する恐れもあり得ます。
そして、通常の訴訟では懲罰的損害賠償が言い渡される恐れもありますが、仲裁であればこの懲罰的損害賠償もありません。
ですので、米国への製品輸出の際には仲裁を選ぶことも考慮されるべきといえます(陪審員は外国製品に対しての判断が厳しくなる傾向があります)。
◆英語の例文・書き方
Any and all disputes concerning questions of fact or law arising from or in connection with the interpretation,performance, nonperformance or termination of this Agreement including the validity,scope,or enforceability of this Agreement shall be settled by mutua| consultation between the Parties in good faith as promptly as possible, but if both Parties fail to make an amicable settlement, such disputes shall be settled by arbitration in Tokyo in accordance with the rules of the Japan Commercial Arbitration Association .
Such arbitration shall be conducted in English.
The award of the arbitrators shall be final and binding upon the Parties.
◆日本語例文・読み方
本契約の有効性,有効範囲,または強制可能性を含む本契約の解釈・履行,不履行,または解除に起因もしくは関連して生じる事実問題または法的問題に関するすべての紛争は、誠実に,かつできるだけ速やかに両当事者間で相互の話合いをもって解決するものとする。
ただし両当事 者が友好的に解決できない場合には,当該紛争は東京において、JCAAの規則に従って仲裁により解決されるものとする。
当該仲裁は,英語でなされる。
仲裁人の裁定は最終的であり,当事者を拘束するものとする。
取引継続のための条項
英文契約書で紛争解決の条項と言えば、裁判管轄や、仲裁条項を思い出されることと思います。
本条項は、紛争が生じている状態でも、その紛争とは関係ない取引は継続するという確認のための条項です。
紛争解決の方法(たとえば仲裁など)について規定した後に入れる,確認の文章です。
◆英語の例文・書き方
Unless otherwise specified in writing,the Parties will continue to honor all commitments under this Agreement during the course of dispute resolution with respectto all matters not subject to such dispute, controversy or claim.
◆日本語例文・読み方
書面にて別途規定されない限り、紛争解決の最中であっても両当事者 は,当該紛争,論争もしくは主張には服さないすべての事柄に関し本契 約におけるすべてのコミットメント(約束)を尊重するものとする。